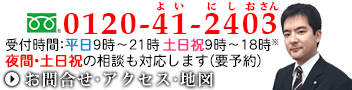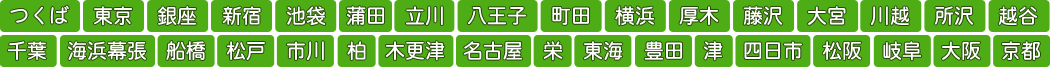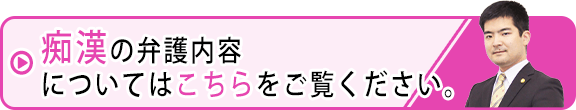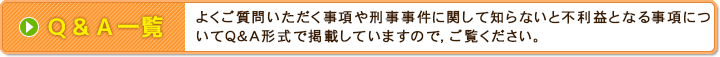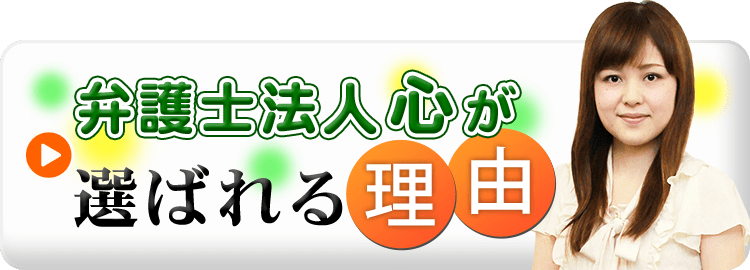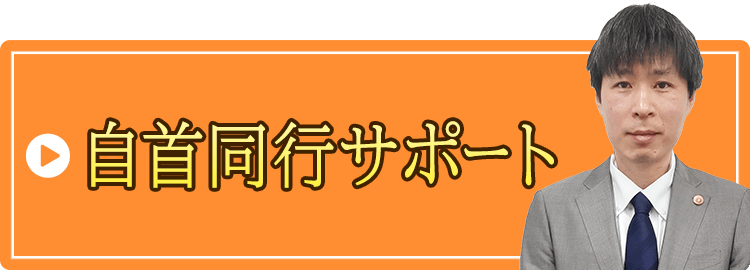「痴漢」に関するお役立ち情報
痴漢が裁判まで発展するケースや裁判を事前に防ぐ方法
1 痴漢事件が裁判まで発展するケース
痴漢事件は、各都道府県の迷惑防止条例違反に留まる場合と不同意わいせつ(旧:強制わいせつ)にまで至るケースがあります。
各都道府県の迷惑防止条例の場合、罰金刑が定められており、初犯の方だと罰金刑になることが多いと思われます。
そして、痴漢を再度してしまった場合、もう一度罰金刑になることもあるでしょう。
例を挙げると初犯は罰金30万円、2回目は罰金50万、3回目は裁判というような形で、回数を重ねる程、処罰が重くなることが一般的です。
3回目で裁判に発展するケースを挙げましたが、個別具体的な事情によっては、2回目で裁判になるケースもあり得ます。
不同意わいせつにまで至る場合、不同意わいせつ事件では罰金がないため、初犯でも裁判となることになります。
2 裁判の流れ①略式手続き
略式手続きは、被疑者が罪を認めている、比較的軽微な事件について、裁判所が100万円以下の罰金または科料を科すことができる手続です。
検察官が略式手続きを選択した場合、テレビドラマでみるような法廷での裁判を開くことなく、裁判官は書類審査で罰金刑等を科します。
書面審理ということは、被疑者の意見を聴かずに罰金刑等の刑罰を科すのですから、憲法上37条1項に定める公開の公判廷において裁判を受ける権利との関係が問題となり得、略式手続を選択するには被疑者の同意が必要です。
実務では、検察官が取調べの際に、被疑者に対して、略式手続の説明をした上で、略式手続によることの同意書を取得します。
略式手続きで罰金になった場合、略式命令の告知を受けてから14日以内に正式裁判の請求が可能です。正式裁判の請求がなされた場合、通常の裁判手続が開始します。
3 裁判の流れ②公判手続
検察官により公判請求されると、裁判所から被告人に起訴状が送達されます。
起訴された後、2か月以内に第1回の裁判の日が指定されることが通常です。
起訴された罪を認めている事件ですと、第1回の裁判で審理が終わり、第2回の裁判で判決が言い渡され、裁判が終了するという流れが一般的です。
裁判は、公開の法廷で行われ、誰でも傍聴することができます。
また、捜査段階で被疑事実を認めていて、公判請求された場合、想定される刑罰は、懲役刑となります。
4 裁判を回避するには起訴される前に示談を成立させる
痴漢事件は、不同意わいせつにあたる場合は、示談しなければ起訴されて裁判になる可能性が高いため、裁判を回避し、不起訴となるためには、示談することが何より重要です。
各都道府県が定める迷惑防止条例にあたる痴漢事件でも、裁判になる可能性が相応にあり、示談することにより、裁判を回避できる可能性は高まるため、示談することは重要です。
裁判になるということは、公開の法廷で裁かれることになり、自身の氏名や犯行内容が法廷で明らかになってしまいます。
また、裁判になる場合は、懲役刑が想定されるため、刑務所に行かなければならないおそれも生じます。
ですので、起訴されて裁判になることが決定する前に、被害者と示談することが何より重要です。
痴漢で不起訴を目指し前科を回避する方法 痴漢は会社を必ず解雇される?懲戒解雇を防ぐ方法