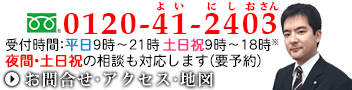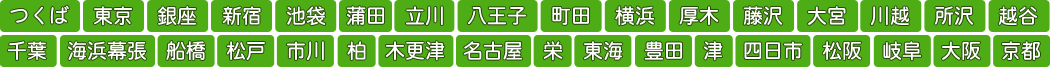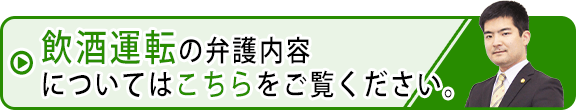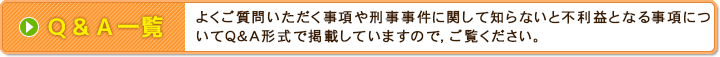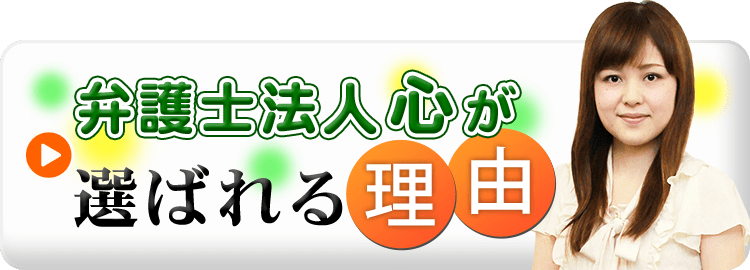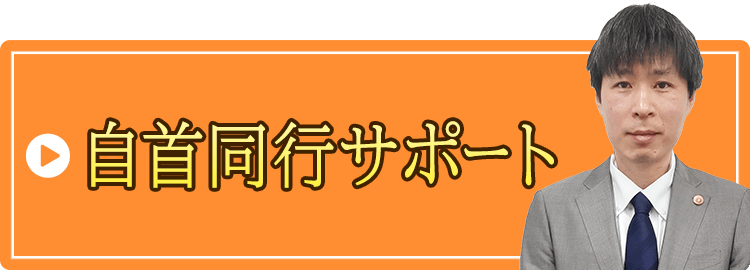「交通犯罪」に関するお役立ち情報
飲酒運転で弁護士を依頼する場合の流れ
1 飲酒運転の取り締まり
飲酒運転は、道路交通法第65条第1項で、禁止されています。
飲酒運転は、酒気帯び運転と酒酔い運転に分類され、酒気帯び運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
飲酒運転の多くは、飲酒検問や警察車両に停められたりすることで発覚しますが、一部事故を起こしてしまったことで発覚することもあり、その場合には過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪となって、より重い罰則に処されることになります。
2 飲酒運転を弁護士に依頼する場合の流れ
⑴ 弁護士を探す
飲酒運転を依頼する場合には、まず依頼しようとしている弁護士が刑事事件に強い弁護士であるかどうかを確認するべきでしょう。
弁護士といえども、すべての法律や事件類型に精通しているわけではなく、それぞれの得意分野を持っていることがほとんどです。
そのため、飲酒運転での刑事弁護を相談・依頼する場合には、その分野に強い弁護士に依頼する方がより良い結果を出すことができる可能性が高まります。
⑵ 弁護士に相談する
相談したい弁護士を探したら、次にその弁護士の所属する事務所に相談したい旨を伝えましょう。
時間帯によっては、弁護士が不在であったり、対応できない場合があるため、注意が必要です。
刑事弁護は、時間との闘いの面もありますので、なるべく早めに対応してくれる弁護士に相談をすると良いでしょう。
⑶ 弁護士に依頼をした後は、相談しながら進めましょう
事故等が発生していない飲酒運転は、被害者がいませんので、自身の反省や今後の更生可能性、飲酒の治療等が刑事弁護活動のポイントになります。
一方で、事故を起こしたりしていて被害者がいる場合には、示談交渉や保険会社との折衝等も必要になりますので、ケースに応じて弁護士と相談をしながら案件を進めましょう。