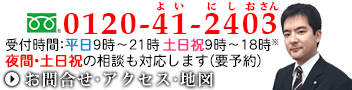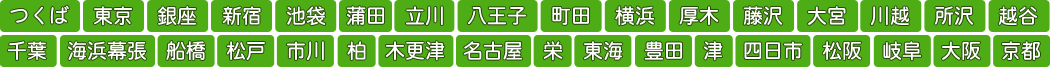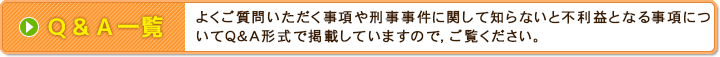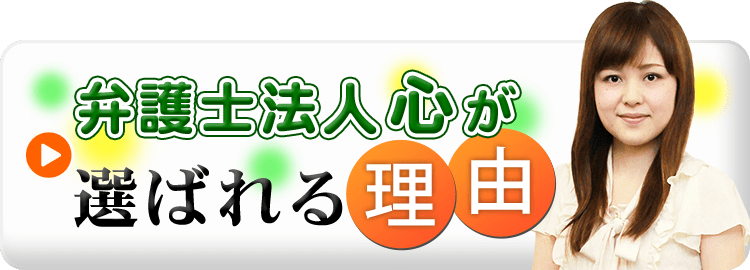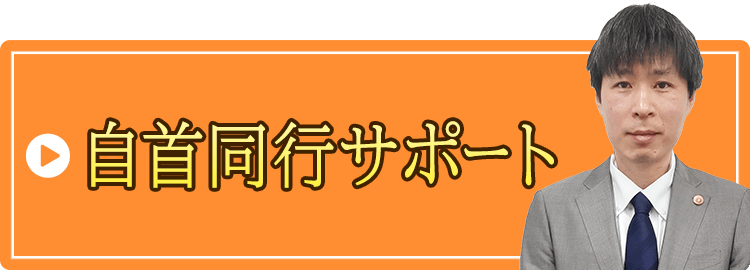「少年事件」に関するお役立ち情報
令和4年施行の改正少年法の概要
1 はじめに
成年年齢引下げに関する民法改正を踏まえて、令和4年4月1日から施行されている改正少年法について、大きな変更点を中心に、その概要を説明します。
2 18歳、19歳の少年を「特定少年」と定義すること
改正少年法は、「20歳に満たない者」という少年について実質的な定義(少年法2条1項)を変更せずに、特定少年を「18歳以上の少年」と定義し(改正少年法62条1項)、特定少年の特別扱いを定める内容となっています。
法制審議会の議論では、少年の定義自体を、例えば、「18歳に満たない者」も検討されていました。
3 検察官送致の特例
特定少年については、罰金以下の刑に当たる罪の事件も逆送が可能となりました(少年法62条1項)。
したがって、原則逆送事件として故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で16歳以上の少年に係るもののほか、死刑または無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件で、犯行当時、特定少年だった場合が、逆送事件の類型として追加されたことになります。
具体的には、強盗や建造物等以外放火などの犯情の幅の広い犯罪類型が対象となったことを意味し、早期の弁護士への相談の重要性が高まったとの評価も可能です。
4 ぐ犯の対応の変更
17歳以下の時期にぐ犯に該当する行為を行った少年についても、特定少年の年齢に達すると、ぐ犯の手続をすすめることができなくなりました。
5 推知報道の解禁
特定少年のときに犯した事件について、公判請求された場合には、その時点から推知報道の禁止を解除することが定められました(少年法68条)。
現状、各マスコミの対応は個別に判断されており、少年法の理念を踏まえた慎重な対応を期待したいところです。
なお、犯行時に18歳未満であれば、推知報道は解除されません。
6 付添人選任権者の範囲拡大
改正前は、少年本人と保護者のみが付添人を選任する権利者と定められていましたが、改正後は、少年の法定代理人、保佐人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹も選任権者とされています。
少年事件の特徴 新宿にお住まいで刑事事件の相談ができる弁護士をお探しの方へ