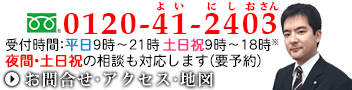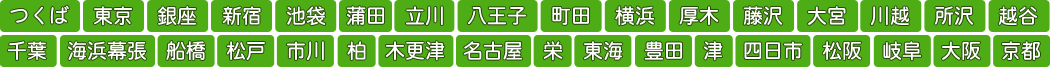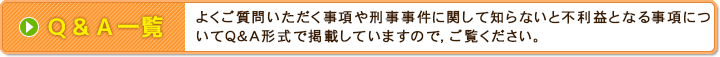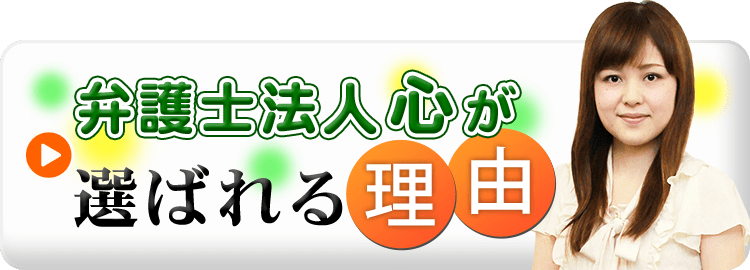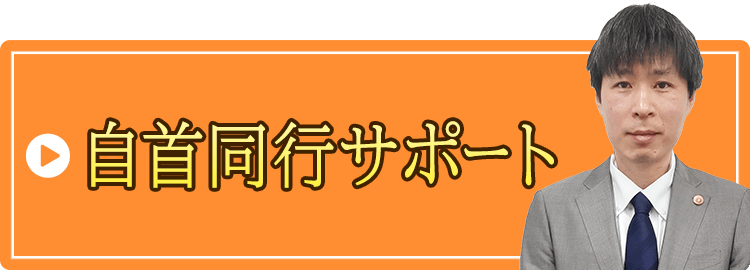「取調べ」に関するお役立ち情報
黙秘権
1 黙秘権の概要
黙秘権は、憲法38条1項に定められている重要な権利であり、被疑者や被告人が、自己の意思に反して、言いたくないことは言わなくてよい権利のことです。
憲法38条1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定めていますが、刑事訴訟法の規定ではその趣旨を拡張し、不利益な供述に限らず、自己の意思に反して言いたくないことは言わなくてよい権利とされています。
また、黙秘権は権利であるから、黙秘したことを理由として、不利に認定されることはありません。
2 捜査での黙秘権の具体的な内容
憲法38条1項を受けて、刑事訴訟法198条2項は、「取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と定めています。
これは、被疑者に対して供述を拒否する権利があることの事前告知義務を捜査機関が負うことを定めたものです。
言いたくないことは言わなくてよいことを事前に告知することによって、例えば、黙秘権のことを知らない人も、黙秘権の保障があることを知ることができ、黙秘権を行使するか否か決定する機会を得られるよう配慮されています。
3 公判での黙秘権の具体的な内容
憲法38条1項を受けて、刑事訴訟法311条1項は、「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。」と定めています。
また、同法291条3項は、「裁判長は、起訴状の朗読が終った後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨」を告げなければならないと定めています。
このように、公判手続においても、黙秘権の存在や内容を事前告知することで、黙秘権を知らない被告人も黙秘権行使の機会が得られるよう配慮しています。
4 黙秘権の行使の方法
先ほど述べたとおり、黙秘権は、捜査手続と裁判手続のいずれでも保障されています。
言いたくないことは言わなくてよいので、黙秘権を行使する場合には、「黙秘します。」と一言述べるだけで問題ありませんし、何も言わずにいるだけでも構いません。
しかし、黙秘権が保障されているといっても、現実には、プロである捜査官から長時間かつ連日の取り調べを受けたり、見通しが分からないといった精神的不安などから、黙秘権を行使できなかったり、当初は黙秘権を行使しても、途中から捜査官の言われるがまま供述してしまうことも少なくありません。
そのため、できるだけ早いうちに、弁護人である弁護士にしっかりと相談しましょう。
弁護士に相談すれば、黙秘権を行使するメリット及びデメリット、当該案件で黙秘権を行使すべきか、黙秘権を行使することでどのような影響を及ぼすかなど、様々なアドバイスをもらうことができるからです。
また、弁護士との相談を通じて今後の見通しが立って不安が解消されることで、精神的に安定し、心が折れることなく、黙秘権を行使し続けやすくなるというメリットもあります。
他方、本人の年齢や精神面等から、黙秘権の行使が難しいと思われる場合もあります。
その場合には、例えば、取り調べ内容を録音・録画するよう、捜査機関側に申し入れる方法があります。
これにより、捜査機関が供述を促すための不当な説得等をすることを防止し、黙秘しやすい環境を作ることができますし、仮に供述する場合でも不当な働きかけがないか事後的に確認することができます。
その他、取り調べで黙秘権は行使せずに供述はするものの、供述調書への署名押印を拒否する方法もあります。
黙秘権を行使すべきか、それとも、それ以外の方法で進めるべきか、事案ごとに最善の選択は異なりますので、早目に、刑事弁護に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
大麻で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット 警察の取り調べを受ける際の注意点