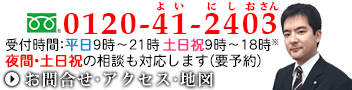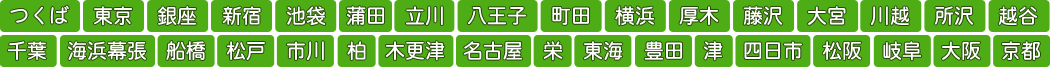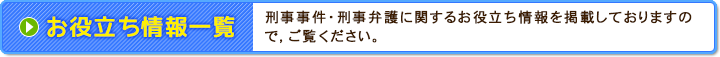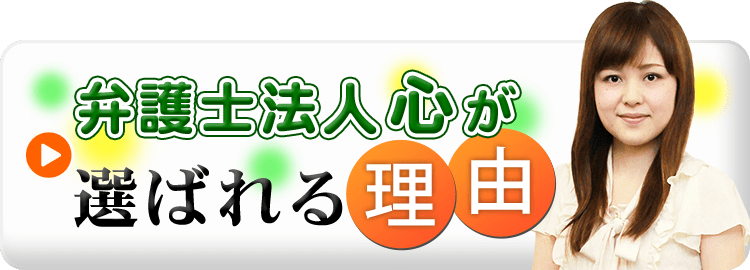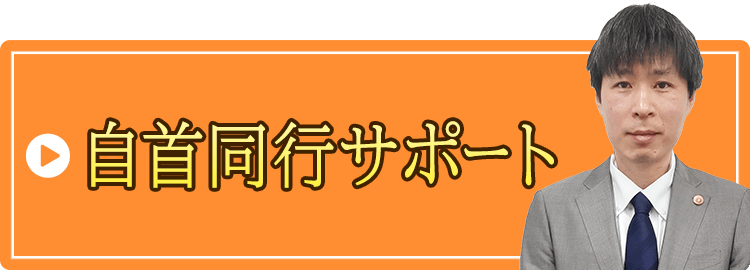「取調べ」に関するQ&A
取調べで黙秘するメリットは何ですか?
1 黙秘権
黙秘権は、憲法および刑事訴訟法によって、保障されている権利で、取調べや裁判において、自己の犯罪事実に関する供述といった、自己に不利益な供述はもちろん、供述したくないことであれば、あらゆる供述を拒むことができます。
2 捜査機関による犯罪捜査
警察や検察官等、捜査機関の立場からすると、犯罪をおこした犯人は、適切に処罰されることが必要であり、処罰するには、検察官が起訴した上で、刑事裁判の手続きを経る必要があります。
そして、刑事裁判で犯人を処罰するためには、検察官が主張する犯罪事実を犯人がおこなったことを証明するための証拠が必要となります。
犯罪をおこした犯人を処罰することが捜査機関にとって重要であることを鑑みると、捜査機関が犯罪捜査をする目的は、刑事裁判になった場合の証拠取集という面が相当にあると考えられます。
捜査機関がおこなう、被疑者に対する取調べも、刑事裁判に備えた証拠収集の一環という面があります。
捜査機関は、被疑者に対する取調べを実施することで、被疑者本人の自白を得ることや、犯罪に至った経緯や動機といった犯行に関わる重要な情報を聴取して、聴取結果を供述調書等の形で証拠化しようとします。
3 取調べで黙秘するメリット
黙秘するメリットについてですが、黙秘しないで取調べで話をした場合、捜査機関に何かしらの情報を与えることになります。
取調べで話をしたうえで、話したことが供述調書にまとめられ、供述調書に署名等してしまうと、情報を与えた上で、捜査機関に書面という形での証拠を作成させてしまうことになります。
反対に、捜査機関による取調べの際の質問等に対して、黙秘を通した場合、捜査機関は、被疑者から何の情報も得られず、ひいては、被疑者の取調べから何らの証拠も獲得できないということになります。
取調べで黙秘するメリットは、容疑を否認している事件で捜査機関に何ら情報を与えないことにより、捜査機関に有罪となる証拠の収集に困難を来たし、嫌疑不十分で不起訴になることがあり得ることでしょう。
4 容疑を認めている事件での黙秘権行使
容疑を認めている事件の場合、一切黙秘権を行使せず、取調べに協力して、事情を話し、供述調書の作成にも応じている事件が多いのではないかと思われます。
少なくとも、容疑を認めている事件であれば、取調べ等に協力して供述調書といった証拠を作成させても、弊害は少ない場合もあると考えられます。
また、容疑を認めている事件であれば、捜査機関を被疑者と対立する敵対者という見方をするのではなく、捜査をスムーズに終わらせることに協力するということが必ずしも悪いことではないといえる場合もありえます。
ただし、黙秘権の行使に関しては、弁護士それぞれによって見解が分かれるところでもあり、容疑を認めている事件でも、原則、黙秘権を行使すべきだという考えもあるようですし、黙秘権を行使すべきは、なによりも個々の事件の内容によって、異なるでしょう。
黙秘権を行使すべきかは、非常に難しい判断を含みますので、詳しくは、弁護士に相談してください。
警察や検察の取り調べの進め方や所要時間、回数はどのくらいなのでしょうか? 取調べの際、弁護士に立会いをお願いすることはできるのでしょうか?